編集者
2016年9月26日
小檜山博氏の「人生という夢」(河出書房新社)を読んだ。ページをめくる度に何度も胸を打たれた。
著者の小説ですでに類似した内容があっても、回想としての切り口が違うと鮮度は失わない。北海道を足場に生きてきた著者の人生を支えてきた人間ドラマが濃密に描かれている。絶望や失意の中で人の絆こそ命綱と痛感する。
この本の末尾で「編集者」たちとの出合いとつきあいが描かれている。鬼編集者といわれる松島義一氏とのかかわりの始めは特に強烈だ。小説の最終校正まで電話のやりとりが夥しい。さらに表現を変えろ、の指摘のFAXが深夜に及び著者は限界を超えていた。松島氏は「俺だって疲れているんだ。おまえ、この試練を乗り越えないと小説家になれないぞ」との激怒は鬼気迫るものだ。
私の場合、鬼編集者には出会ってないが、担当編集者の親切な指導を受けて学んできた。推敲不足が書き直しにつながる。書き手はある意味で熱中状態にあるので客観性が弱点になる。編集者はまっさらな頭で読んでくれるので文章の欠点や説明不足などに気づいてくれる。
私を起用した新蔵博雅部長。担当者では青山実、伊藤一哉、高田昌幸氏などの顔が浮かぶ。富田友夫氏とは20年以上のつきあいである。
16年ほど前だが「朝の食卓」というコラムを書いていた。担当が高田昌幸氏だった。原稿を送ると、彼から電話がくる。説明に納得し、文を直すことに同意する。そのころ、札幌に出かけた折に北海道新聞社に寄った。顔見知りの報道部の方々にあいさつした。高田氏には「日本ジャーナリスト大賞受賞おめでとうございます」と祝福した。「そんな浮かれている心境ではないよ。ちょっとお茶でも飲みませんか」と彼は言った。あいにく私はホテルでの表彰式をひかえていたので、事情を説明して断わった。
これは後で分かったことだが、当時は「道警裏金問題報道」をめぐって社の経営陣と報道現場で乖離が生じて揺れていた時期だった。高田記者は私に何か話したかったと推察できた。誰にでも話ができる問題ではなかった。
その後、高田氏は左遷の憂き目を経て退職した。「真実」という彼の本が出版されて私は読んだ。組織に身を置く個人の生きがたさを痛感した。彼は故郷に帰りそこの新聞社に務めている。近くに旅行する機会があれば「飯でも食いませんか」と私から声をかけたい。懐旧の情に満ち、お礼のことばと質問が私の口からあふれ出るにちがいない。
◎プロフィール
(よしだまさかつ)
北海道新聞「朝の食卓」元執筆者。十勝毎日新聞「ポロシリ」前執筆者。「流転・依田勉三と晩成社の人々」刊行。










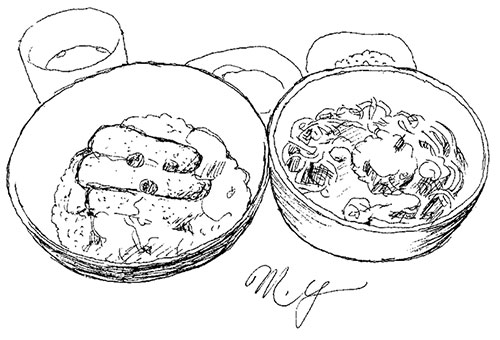







 株式会社 ヒューマンリンクス
株式会社 ヒューマンリンクス